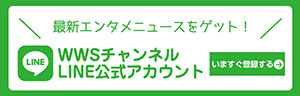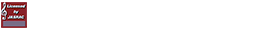そんな言葉で本ツアーの意志を説明していたMAH。『BEWARE』という作品を掲げるツアーであったと同時に、ロックバンドと、ロックバンドを好きな人々が何と闘い続けてきたのかを改めて喚起する「牙を剥くための正義」がこのツアーの心臓になっていたことは、あの空間をともにした人々に真っ向から伝わったことだろう。
 Photo by スズキコウヘイ 画像 4/6
Photo by スズキコウヘイ 画像 4/6
そして何より、その意志がそのまま2者のライヴに映っていたことが素晴らしかった。10-FEETのTAKUMAは2日目のステージで「いろいろ言い合って、傷つけ合って。指摘したり議論したり、それが誹謗中傷になって。俺らはいつまで傷つけ合うんやろうか。優しさは想像力やで。励ましたり、好きやと伝えたりするのも、想像力と勇気と心意気。そして、伝えようと思ったらたくさんの言葉が必要や。表情とトーンでも伝わり方は違う。ライヴっていうのは、音楽を通すだけで気持ちが誤解なく伝わる奇跡の場所。ここが、コロナ前よりもっといい場所になっていくように」という言葉を発し、取り戻すのではなく今から作り上げていくのだという意志をgoes onに託してステージを降りていったが、これもまた、SiMと共鳴する精神やロックバンドが自分達の場所を自治してきた理由を端的に表したひと場面だったと思う。1日目はTAKUMAとKOUICHIが、2日目はTAKUMAとNAOKIがSiMのTシャツのペアルックで登場して笑いを誘っていたが、笑って泣けて飛べる10-FEET節を全開にして、新旧問わないセットリスト全体が上述の言葉をそのまま体現しているようだった。どの時代の楽曲も、優しさの在処を問い、優しくあるための葛藤を生々しく表していて、そしてそれは人とともに生きることの喜びや難しさに実直であり続けた証のように響いてきたのだ。コロナ禍だろうと、どんな時代だろうと、優しくあれ。人の痛みを想像し、自分と人が笑っていられる場所を自分達で守り続けろ。そんなメッセージは、痛みと閉塞感にまみれ、愛する場所すら奪われそうになった時代に改めて真理として響くのである。
そしてSiMも、2日間通して新旧の楽曲を織り交ぜたSiM絵巻のようなライヴを展開した。初日はPUNK ROCK iZ COMING(2011年『SEEDS OF HOPE』収録)やIKAROS(2014年『i AGAiNST i』収録)、2日目はSUCCUBUSやAといった、いわゆる「レア曲」も織り交ぜていたわけだが、ニューメタルとダブとポップパンクが交錯する複雑な展開を歌謡的なメロディで貫いていくSiM節が、特にコントラスト高く表現されている楽曲達である。2020年から2021年にかけて行われた無観客配信ライヴで全5作のフルアルバムを曲順通りに再現するパフォーマンスを行ったことが大きいのだろうが、過去楽曲を再発掘したり、過去楽曲に新たなグルーヴを宿したり、SiMを研ぎ直す鍛錬が各楽曲に表れていた。特にIKAROSのように「メロディックパンクmeets歌謡曲」な楽曲、PUNK ROCK iZ COMINGのようにスカとポストハードコアが目まぐるしく交差する楽曲では、改めてSiMの音楽的な要素を整理整頓できたからこその硬軟自在なアンサンブルが展開されていった。ニューメタル、パンク、ダブ、オルタナティヴロック、ポップパンクといった音楽的素養を合体させるSiMの背骨は、その音楽が生まれた年代やシーンにかかわらずに音楽を食う雑食性と、たとえば2000年代に仲の悪かったニューメタルシーンとポップパンクシーンの歴史を知った上でドッキングさせてしまう「理解があるからこその節操のなさ」から生まれたミクスチャーである。しかし、その一見カオティックな音楽に通底しているのは、各時代で生き抜くための武器として鳴らされたレベルミュージックの精神性である。そこ一点であらゆる年代のロックを繋ぎ、そして日本的なメロディで筋を通す。上記した楽曲達は、今改めてSiMの音楽的カオスをシンプルに伝えるもので、声出し解禁のメッセージやロックバンドとしてのスタンスと同時に、コロナ禍での試行錯誤を経て音楽的にも研磨されたSiMの姿が克明に浮かび上がるライヴだった。その上でさらに言えば、The Rumblingが『進撃の巨人』とともに世界中に波及したことも、SiMの音楽的な振り切れ方に直結したはずだ。シンプルなポストハードコアを荘厳な響きでぶっ放したThe Rumblingは、SiM史上でも類を見ないほどシンプルで、美しいメロディで一点突破する楽曲だった。SiMの音楽細胞を組み合わせるというよりも、削ぎ落として磨き上げた楽曲。そのシンプルさとメロディの強さが世界的な歓迎を受けたことによって、各要素をより一層シンプルに鳴らせば刺さるという確信を得たのだろう。『BEWARE』に収録された各楽曲が表す通り、ミクスチャーな楽曲を構成する各要素の解像度が増し、それがそのまま、彼らの音楽に半端じゃない推進力を与えている。実際、Blah Blah BlahやKiLLiNG ME、CROWSといった楽曲の瞬発力も、合唱ができるか・できないかという部分ではなく、あくまで音楽の跳躍力と硬軟自在なアンサンブルに宿っていた。客席に目をやっても、思い思いの動きどころか、名前のないダンスで己の衝動を発している人々の姿が眩しい。SiMの音楽の中にある痛快なカオスは、「生きたい」も「死にたい」も「飛びたい」も「沈みたい」も同時に抱えてしまう人間の倒錯した感情を一気に表すものなのである。ダイヴやモッシュがなくとも、その音楽の通りの光景が目の前に広がっている。
さらに、楽曲への解釈の深まりは、アンサンブルに限った話ではなかった。本ツアーのテーマ曲だと紹介されてから雪崩れ込んだANTHEMがまさにそう。この楽曲が制作された2010年当時は、日本のラウドミュージックをメロディックパンクが席巻していた。そこに海外のニューメタルとレゲエを組み合わせたSiMの音楽が入り込むために、ブラストビートを取り入れてモッシュとダイブを引き起こさんとしたのがANTHEMという楽曲である。さらに、観客の手と拳が挙がるかどうかが対バンライヴのバロメーターだった当時、なんとか手を挙げさせるようにして歌われていたのが<I’ll take your hands>という一節だ。それが今、「いつかお前らの手を引いて行く」という意味合いを超えて、聴く人を新時代へ誘うためのヒロイズムを真っ向から響かせる楽曲に変化している。「真っ向から闘って勝ち取りましょう」というMAHの言葉や、ロックシーン自体を背負う誠実な活動や、その上でSiM自身が夢を叶えんとしている今この瞬間がすべて自信と確信に繋がり、そして彼らのヒロイズムになって、音楽とライヴを輝かせているのだ。
「コロナにびくびくしながら過ごすのは今年が最後だと考えていて。みんなも、一緒に闘う気持ちでライヴに来てくれたらいいなと思ってます。……自分を貫き通すのは、誰かとぶつかり合ったり誰かを傷つけたりするためじゃない。自分を貫くのは、自分の大切なものを守るためだ。それがSiMの闘い方。強く生きよう」