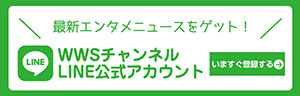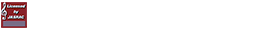12月8日と9日に、SiMが「TOUR 2022 "BEWARE"」の最終公演を東京のZepp DiverCityで開催した。本ツアーは全公演でゲストバンドを迎えて実施されたが、コロナ禍以降は収益的な面でも感染症対策の面でも対バンイベントが減る傾向にあったライヴシーンを徐々に拓き、ロックバンドが交わる場所としてのステージを取り戻していく意識が、このツアーの多彩なゲストの面々に繋がっていた。そして最終公演2デイズは両日ともに10-FEETをゲストに迎えたわけだが、「京都大作戦」をはじめとしてロックバンドの居場所自体を守り続けたバンドとの対峙自体がSiMからのメッセージだったように思う。SiMもまた、自分達以上にロックシーン・ライヴシーンを背負ってこのツアーを開催したからだ。
【写真】全国ツアーファイナルで10-FEETと対バンしたSiM(6枚)
本ツアーは、「声出し解禁」を掲げて開催された。7月20日、ツアー開催発表と同時に公開された声明文でMAHは「一歩だけ踏み出してみる。調子にのって三歩、四歩は踏まない」という言葉を用いていたが、これはSiMとしての一歩を表したもの以上に、コロナ禍におけるライヴシーンを推し進める意味合いがあった。そもそも丁寧に声明文を公開し、ガイドラインに則った上での声出し解禁についての意図を説明すること自体にSiMの誠実なスタンスが映っている。今年のDEAD POP FESTiVALのステージでも「俺らは2年間、ライヴや音楽を守るためにしっかりやってきた。そろそろ一歩進む時だ。ただ、俺らだけ先走っても意味がない。仲間のバンドが現状のガイドラインに対してどう考えているのかを聞いたり、各所と丁寧に話したりした上で、堂々と次の一歩を踏みたい」という旨の話をしていたわけだが、感染症対策のガイドラインを遵守し、各地のライヴハウスや周囲のバンドとコンセンサスを逐一とりながら進んできたのは、コロナ禍に入った当初から「クラスター」という言葉で社会的な標的にされたライヴシーンを守るためであり、自由を自分達の手に取り戻すためなのだ。つまりSiMは、ロックシーンやロックリスナーに対して働きかけてきたのではなく、社会や世界に対してロックバンドの存在証明を果たし続けようとしてきたのである。SiMがルールやガイドラインを飲み続けてきたのは、パンデミック下の世界から矢を向けられてしまうからではない。文句を言わせず自由を表現するためなのだ。今現在、ライヴハウスや各バンドの考え方によって、声出しやモッシュ、クラウドサーフに対するスタンスはバラバラになっている。中にはガイドラインなど知ったことかという考え方のもとに行われるライヴもあるわけだが、その中でSiMは、シーン全体の足並みが揃わないことを否定するわけでもなく、足並みを揃えようと訴えるのでもなく、真っ向から自由を勝ち取りにいくために、「50%の動員ならば大きな声を出していい」というルールを遵守してきたのである。
「もうそろそろ声出しくらいさせてくれよっていう気持ちで始まったツアーです。今もガイドラインがあるわけだけど、実は発声そのものを禁止しているわけではないんです。継続的な発声は避けて、断続的な発声はOKっていう、発生における基準が設定されていて。でも、(フルキャパシティのライヴにおいて)1曲のうち25%なら声出してもいい、会話より小さい声ならOKっていうルールを設定されても、意味がわからないじゃないですか。曖昧過ぎるし、その場にいる人で考えて声出してくださいって言われても難しい。なんなら、そういう曖昧なルールの上では『私は歌うのを1コーラスで我慢したのに、隣の人は2コーラス歌ってた』っていう気持ちになる人が出てきてしまう。そうやって喧嘩とか言い合いが起こるほうが不毛だし、内輪で喧嘩してる場合じゃない。だからSiMは、ありかナシかでルールを明確化するほうがむしろ個々が自由に楽しめてハッピーになれると考えてライヴをやってきました。ここZeppは、声出しを控えてくださいっていうルールを守っているから、今回は声出しをナシにしてフルキャパシティのライヴにしました。……ライヴシーンの空気的には、声を出すくらいは大丈夫だっていう雰囲気になってきてるし、声出しを解禁しているバンドも増えてきてる。でも俺は、コソコソやるのが嫌いなんだよね。堂々とやれるようにしたくて、今回みたいなツアーを回ってきました。ちょっと待たせちゃったけど、堂々と、思い切り遊べるように。一緒に闘い抜いて、勝ち取りましょう」